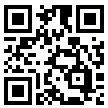人口減少社会のまちづくり
中央学院大学教授 福嶋浩彦(元 千葉県我孫子市長)
我孫子市長の経験を活かした講義をして頂きました。
≪人口減でも持続可能な仕組みに変える≫
〇 わがまちの人口減を小さくするには、どこかのまちの人口減を大きくする必要がある
⇒人口奪い合いの先に地域の未来はない「ゼロサム」
〇 人口減少してもみんなが幸せになる、持続可能な仕組みをつくることが大切
周辺の自治体と共有する(競技場、音楽施設etc)、民間企業と協同することによる多機能化、複合。
〇 人口減少の時代 多様な人が対話し、知恵を出し合い、選択と創造をする
≪自分ごと化会議の良いところ≫
〇 討論ではなく、対話の場
対話は、自分の意見も、相手の意見もどんどん変わっていくことが目的
〇 対立する問題でも、実は「まん中の人」が沢山いて、この人たちこそ合意づくりをリードする。
〇 信頼関係にもとづく対話で、修正が可能な柔らかい社会決定ができる。
講義最後30分は質疑応答、学生による質問に講師による丁寧な回答がありました。
講義終了後も、学生同士で意見交換が行われたり、これからもまちづくりに積極的関わっていける事を願っ...
昨年までおこなっていた「いきいきシニアコース」を、今年度から「もりやいきいきコース」にリニューアルしました!!
シニア限定ではなく、幅広い年齢層で募集をし、
・健康づくり
・暮らしに彩を添える
・食を楽しむ
をテーマに世代を超えて、心身ともに充実した生活をおくるためのヒントを学ぶコースとなりました。
その第1回目は、筑波大学名誉教授の田中喜代次先生に“人生100年時代におけるスマートな生き方~健幸華齢への道”について総論的な内容でご講義いただきました。
田中先生が提唱される「スマートな生き方」を6つ教わりました。
運動、栄養、お薬などの重要性について、データを示しながらご説明いただきました。
中でも、この時期気をつけなければいけない「熱中症」については、室内で倒れるケースが圧倒的に多いようで、その対策について教わりました。
また、フレイルについて詳細にご説明いただき、参加者の理解が進んだようです。
80歳であれば、フレイルでも“サクセスフルエイジング”を実現しており、人生の質は高いでしょうというお話でした
世代ごとに様々な健康問題が出てきますが、守谷市に住みながら、健康でいきいきと生活をおくれると良...
2025年度 初回の守谷を知るコースは「守谷の開発史」と題し、守谷市の行政史と概要について、NPO法人協働もりや代表理事で正安寺74代目住職の豊谷如秀(とよたにゆきひで)さんにお話を伺いました。
第1回目の講義ということで、参加受講生の住んでいる地域とお名前だけの自己紹介のあと、担当の運営委員を紹介してスタート!
茨城県の自治体で2番目に小さい市である守谷市の軌跡や、アサヒビール工場などの企業誘致、つくばエクスプレス開業までの苦労話を伺いました。
これから1年間、10回の講座をどうぞよろしくお願い致します。
真夏日の中、25名の参加で迎賓館見学ツアーを実施しました
守谷駅に午前9時に集合し、秋葉原で総武線に乗り換えて四ッ谷駅で下車。
乗り換え前後に必ず人数確認して安否確認(笑)
80代の方も元気に歩いて、11時の予約時間に間に合いました。
まずは主庭で記念撮影
国宝の噴水
ちょっとアップで撮影
迎賓館として蘇った明治の西洋宮殿
館内はすべて撮影および飲食禁止のため、入館前にしっかり水分補給してから見学しました。
最後に正門前にて記念撮影
見学ツアー終了後はそれぞれのグループに分かれて、買い物に行く人やランチを楽しむ人など楽しく過ごすことができました。
みんなのまちづくり入門コース
新しいコースが始まりました。
一般財団法人地方創生戦略研究所
代表理事 井手よしひろさんによる講義
地域の特性やニーズに基づいた持続可能な開発計画を策定など
とても分かりやすく、守谷市の課題に触れたお話しです。
守谷市のスマートインターチェンジ整備計画、総合運動公園整備計画、都市軸道路整備の3大プロジェクトをSDGsの視点から検証
学生からの積極的な質問に丁寧に説明をして頂きました。
6月7日(土)は、好天のもと、もりりん中央(中央公民館)にて開講式でした。本年度申込者延べ125名、その半数近くが出席されていました。受付を担当した運営委員は「新規入学者が多く、年齢構成でも若返りが目立ちます」という手応えを感じたそうです。
冒頭の私(学長)挨拶では、本年度応募者数、入学者数のご説明、毎年のコース定員と抽選制度の見直しについて、さらに、もりや市民大学の設置理念の確認、運営委員会の実態に関するご説明、最後に、運営委員が受講生に期待することを順次お話しました。
後日、受講生と運営委員の双方から感想意見が寄せられました。いくつかご紹介しましょう。開講式について「思ったより出席者が少ない」、「運営委員の紹介がとても良かった、市民大学を身近に感じた」、「良いスタートでした」入学者について「不合格者ゼロは良かった」、「若い方がもっといると言い良い」などのご意見でした。
松丸市長の基調講演は「地方分権一括法施行後の地方自治のあり方」という少々堅苦しい標題で始まりました。松丸市長が「地方分権一括法という法律をご存じの方いますか?」と問いかけたところ、会場はほぼ無言、市長はやや...
今年の市民科学ゼミは、12名の参加で6月7日(土)にスタートしました。
市民科学ゼミは、参加者が守谷市でやってみたいことや各自が抱いている問題に対する課題などを参加時に持ち寄ります。
そして、1年かけてこの課題に対して研究活動をおこない、最終的に「調査」「企画」「提言」という形でまとめて発表します。
今年度は6月~10月にかけて、研究の方法やファシリテーションなどの知識を学びます。
11月~3月にかけては、各自の研究活動の進捗を発表し、まとめていきます。
昨年同様、茨城大学社会心理学の伊藤先生と「つなぐ つながる つむぎだす」通称「つーラボ」の先生方にアドバイスなどいただきます。
1、2回目はオリエンテーションということで、ゼミの進め方の説明や自己紹介などをおこないました。
参加者のうちの10名は昨年からの継続です。
2年目はさらに充実した研究活動になるのではないでしょうか!
先週末、6月7日に2025年度のもりや市民大学・開講式が執り行われました。
今年も多くの方が受講してくださり、リニューアルされたコースもあって更に凝縮された楽しく学べる講座が盛りだくさんです!
学長の挨拶から、オリエンテーション。
わたし達、運営委員の紹介とご挨拶。
後半は松丸市長による基調講演「地方分権一括法施行後の地方自治のあり方」
守谷の歴史から始まり、地方政府の自立、現状の課題と対策など
今の守谷と未来の守谷への思いを聞かせていただきました。
2026年以降の守谷サービスエリア付近や新守谷付近の開発が気になりますね!
いよいよ、各コースの講座が始まります。
一年間よろしくお願いいたします!
(守谷・四季の里公園)
新緑の季節が来ました。どの植物も葉を広げ、枝を延ばしてきます。さて、私たち人間も大いに葉を広げ、枝を延ばしたいものです。そのためには何をすればよいか?その答えが「もりや市民大学」にあります。そうです、「守谷を知るコース」では身近な情報を楽しく学ぶというコンセプトで教室が満杯になります。「もりやいきいきコース」では世代を超えて心身ともに充実した生活をおくるためのヒントが満載です。どちらも募集人数を超過する人気コースであるため、抽選で外れる方が出ることを心苦しく思っています。
ところが一方、5月病と呼ばれる心身の不調が現れることも報告されています。環境変化で張り切っていた4月を乗り越え、連休で一息ついた後、心と体のバランスが崩れやすくなるそうです。環境変化への対応力、適応力が関係しているのでしょうか。とにかく、初夏、梅雨、真夏へと変化していくこの季節、互いに励まし合いながら元気に過ごしたいものです。
最近気になるのは、やはり健康や寿命の話題です。今年1月26日に開催した市民大学公開講座で、講師の阿部皓一さんが「日本人の平均寿命が延びた第一の理由はなんでしょうか?」と聴衆に質問されまし...
今年も18人の参加で弘経寺「千姫まつり」へ。
朝9時守谷駅から水海道駅に向かい、バスにて千姫祭りの弘経寺へ行き、
観光大使で演歌歌手の丘みどりさんが出迎えて下さいました。
11時からウォーキング。鬼怒川土手伝いに約3キロの散策
途中安養寺に立ち寄り、ラッキ-にもご住職さんが快くお寺の内部を見せて下さり、
前日の雨模様とは打って変わって、五月晴れのウォーキング日和を楽しむことができました。
感謝状、功労賞、フェロー、学位記、修了証、卒業証など、この年度末年度初めには沢山の賞状が授与されます。受賞された皆様、おめでとうございます。ところで、受ける方ではなくて授与する側に立って初めて気づくことがあります。それは、この種の賞状には句読点が無いことです。句点、読点は文章を読みやすくするために欠かせない記号ですが、なぜか賞状には句読点が使われていないことに初めて気づきました。
海外でも多くの賞状が授与されます。そこで、英語圏の賞状でも句読点は省略されるのかを調べてみました。気づいたこととしては、賞状の本文には句読点は使われていない、ということでした。ただし、同じ賞状の中で別途説明文や激励文が添付されていることがあり、そこでは句読点が使われ、ビックリマークなども適当に使われているようです。英語圏では「~~に関する賞与」といった名詞形で本文を書くので、句読点は不必要なようです。
改めて過去に受け取った表彰状などを眺めてみると、確かにどこにも句点、読点が記載されていない、不思議な書面ばかりでした。そして、そのような書面はなぜか格調高く見えるのです。ところが、最近のメール交換で...
「炭素がつなぐ自然と私たち」
〜植物と地球の歴史を知り未来を守る〜
新年度最初の講座は、もりや市民大学運営委員で東京大学名誉教授の松本雄二さんの講演でした。
今回の講座は、東大教養学部での講義内容を凝縮しての案内なので、東大に行かなくても無料で講義が聴けるという、ありがたい機会になりました(笑)
「デコ活」ってなに⁉️
筆者は初めて接する言葉でした。
デカボ(decarbonization=脱炭素)+エコ活
だそうです。
炭素は二酸化炭素として大気中や陸地、海水中、地中に存在。
原始地球では炭素は二酸化炭素としてのみ存在し、原始地球の大気は現在の金星大気に似ているそう。
そして約46億年前から地球の冷却が進行して海ができ、植物がこの世に出てきたのは4億3,000年前と、気の遠くなるようなスケールの話です。
1860年以降の気温変化を見ると「太陽活動の変化と火山活動」と「二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素の3つの温室効果ガス」の両方を同時に考慮すると、実際の気温変化と一致するそうです。
そして 樹木は死んだ細胞の蓄積体…とのこと。
終了後のアンケートでは、さまざまな感想が寄せられ受講者の関心の高さが感じら...
今年度最後の守谷を知るコースの講座は、守谷はちみつ夢プロジェクトの楽しくおいしい講座でした。
みつばちってどんな生き物?
日本ではちみつを取れるのは、ほぼセイヨウミツバチ。ニホンミツバチは飼育が難しいそうです。
女王蜂は1匹であるのは知っていましたが、働きバチはメスだけとはびっくり。
てっきりオスだと思っていました。
オスは殖のために存在していて働かないそうです。
またハチといえば針で刺すイメージが強いですが、
刺すのは働きバチ(メス)だけで、女王蜂は産卵のためにあり、雄ばち(オス)には針がありません。
針のないハチがいたこともおどろきです。
女王蜂を探すクイズも!
難しい!
慣れるとすぐに見つけられるようになるそうです。
講座では実際に使われている巣箱や道具も持参していただきました。
びっしりといるみつばち、写真なので安全です。
こちらは実際に使っている道具です。
なんと、貴重なはちみつの試食もありました。
春と秋のはちみつだそうで、春は色が薄くあっさり、秋は濃厚な味と違いを知ることができました。
おいしかったです!
守谷はちみつ夢プロジェクトの立ち上がりや一年の活動な...
6月からスタートしたいきいきシニアコースが本日最終日となりました
最終回は「自分にとってのいきいきシニアを考える」ということで、運営委員の高木さんから実体験を交えたお話がありました。
高木さんはご病気がきっかけで、ボランティア活動を始められ、「ありがとう」といわれることが大変うれしかったとおっしゃっていました。
現在も、もりや市民大学運営委員の副学長をはじめ町内会においても様々な活動をされており、個人的に尊敬する大先輩です
実は、運営委員を今年度でご卒業されますので、この場を借りて、、、、
長年にわたり、大変お疲れ様でした。今後ともぜひお力添えください♪
後半は、コーヒーを飲みながら、各自1年間を振り返り、参加者の方のご感想をお聞かせくださいました。
・自分は何のために生きているのか、、、?ボランティアを始めてみようか!
・現在までの限られたコミュニティではなく、様々な方の意見を聞けたり、友人ができた!
・地域のコミュニティに参加することで、安心して守谷市で生活できるようになった!
・新しい情報なども聞けて、大変良い学びになった!
などなど、うれしいお言葉をたくさん聞くことができました
み...
【国際交流員から見た守谷と日本】
2023年8月 守谷に赴任して2年目の国際交流員シルビアさんから話を伺いました
まず自己紹介で出身地のデュッセルドルフについて。
デュッセルドルフにはドイツ最大の日本人コミュニティがあって、日本企業が500社以上、日本の幼稚園や学校もあり、住んでいるだけで日本食のレストランやお店を見ることができたそうです。
シルビアさんは琉球大学や京都大学に留学し、都内の企業でインターシップの経験もあり、日本語が堪能です。
守谷では国際交流員としていろいろな活度をされています。
さて、ドイツは何カ国と接しているでしょうか?
なんと9カ国と接しているそうです。
島国の日本とは違いますね。
ドイツと日本の違いを感じたのは、
日曜日…
アイコンタクト…
など、いくつかあるようです。
そしてシルビアさんから見た守谷は、
「みどり」
「カラフル」
「街がきれい」
「お祭りも楽しい」
「子どもも大人も勉強熱心」
「子どもにとって素晴らしい環境」
「国際交流・ボランティア活動が多い」
という印象とのこと。
守谷にずっと住んでいると、その良さに慣れてしまい当たり前のように思えますが、...
3月は、卒業、退職、異動など、個々人にとって変化に富んだ月になります。それを祝って梅や桜も満開になり、記念写真を撮る人々が群がります。守谷市でも「もりや河津桜里親の会」が主催する維持管理の催しが開かれます。朝が早くなり、昼の時間が延びることもあって人々の活動が活発になって来ました。早朝の高速道路上では車の数が多くてびっくりすることもしばしばです。
そんな中にあって、もりや市民大学でも運営委員の世代交代が着々と進んでいます。当面、5人の現職が引退し、4人の新人が参入する予定です。引退される運営委員はこの13年間献身的なご尽力を頂いた方ばかりであり、いくら感謝してもしきれないほど多くの貢献をされました。毎年のプログラムを組み、講師の方々と交渉しながら一つ一つの講座を設営し、受講生を受け入れる実務を行い、開講式から修了式まで一切を手作りで仕切って来ました。それだけでなく、早い段階から次年度の開講計画に着手し、更には長期的な市民大学の在り方についても検討を怠りません。
いささか自画自賛になって来ました。それよりは「市民大学の出口」と言われているように、受講生のその後の活躍こそが財産です。...
本日、2024年度市民科学ゼミ成果発表会が中央図書館視聴覚室でおこなわれました。
今年度テーマを決めて各自がおこなった活動を企画、提言、調査という様々な形で報告がありました。
9組10名の方がパワポで資料を作成し、質疑応答を入れて一組25分の持ち時間で、熱い思いを伝えられていました。
元気なシニアが守谷市でいきいきと過ごすための提案や、健康づくりとしてのテニピン(テニスとピンポンが合わさったもの)やウォーキングの普及、
環境や交通網の問題や提案など様々なテーマで興味深い内容でした。
市の職員や運営委員、市民の方々が聞きに来られていました。
13時10分に始まり、17時半まで長丁場でしたが、最後に伊藤先生からの講評がありました。
この市民科学ゼミが守谷市の市民シンクタンクになり、市民研究者の育成やローカルな問題に目を向けながら、グローバルな世界的の問題も
取り上げていくようになると良いですね!というお言葉がありました。
みなさん1年間大変お疲れ様でした。
本日の発表がここでとどまらず、今後の展開につながればよいですね
今回の「もりや市民大学友の会」のイベントは、首都圏外郭放水路(埼玉県春日部市)〜キッコーマンもの知りしょうゆ館(千葉県野田市)の見学でした
まず地下神殿の概要を学んでから、116段の階段を下りて地底探検と記念撮影
地下神殿の見学後は南桜井駅までコミュニティバスを利用。
春日部市らしく、コミュニティバスの中は「クレヨンしんちゃん」が行き先案内
南桜井駅から野田市駅へ移動して、
野田市駅が高架で(高価な?)駅に様変わりしていて驚きました!
キッコーマン工場の見学
見学後は「しょうゆと豆乳のミックスソフトクリーム」を美味しくいただきました
今回は前回に引き続き、〜守谷市でのシニアの活躍の場を探る②〜
守谷市内で活動されている
「健幸ウォーキングもりや」
「守谷ネイチャーライフ」
「スマートライフ倶楽部」
の代表の方からお話を伺いました。
まず「健幸ウォーキングもりや」の原さんから活動内容を伺い、守谷のウォーキングコース数カ所を紹介いただきました。
原さんがウォーキングに関心を持ったのは市民大学での講座を受講したのがきっかけとのこと。
続いて「守谷ネイチャーライフ」の佐合(さごう)さんから、活動の目的やその後の経過について
会の目的は、
守谷市内の自然環境を守り、市民が自然に親しみ、楽しめる環境づくりを目指す活動を行うことだそうで、
こちらも市民大学でのスタートアップ講座の受講生7名が自主的に組織を設立したそうです。
その後ホームページを作成し、情報の発信や守谷市への提言を行っています。
続いて、
「スマートライフ倶楽部」の上西さんから、SLC活動の紹介
現在、私たちの生活にはスマホが必需品となっており、せっかく持っているなら少しでも使いこなして生活に役立てたいですよね。
最後に上西さんから、講座のまとめとなるような言葉を...
守谷を知るコースの15回目は、常総映像ビデオクラブの活動紹介
常総映像会員の渡邊英昭さんがお話を聞かせてくれました。
2004年に設立されて、創立20年になる常総映像ビデオクラブは毎月例会を開いて情報交換や映像作品上映などの活動をしています。
年に二回の撮影会を行い、12月にはコンテストを開催しているそうです。
創立20周年の記念上映会が昨年の秋に開催され、みんなで観て審査をして投票。なんと180人の参加者だったそうです。地域貢献活動もされていて、子ども食堂もりんくるの活動紹介映像を見せていただきました。
また、市内の大野小学校の米作り体験学習と田んぼリレーの映像も見せていただき、子供達の楽しそうな様子を見ることができました。
守谷で生まれたビデオクラブは、みなさん映像について勉強され、自分の趣味を深めつつ、地域貢献もされていて、とても楽しそうでした。
ただいま会員募集中とのこと。
自分で映像を撮って、編集する技術を学べるのは面白そうですね!
今年度、最後の公開講座は、抗老化の分子栄養学-100歳まで元気で暮らすために-
武蔵野大学薬学部SSCI研究所・分析センター長で2023年度の日本ビタミン学会功績者でもある阿部皓一先生の講座でした。
100歳まで元気暮らせるためどうするか?
若いと思った時に若くなる!
「自分は若い、老けていない」と思うポジティブ効果が1番大切だそうです。
長生きの秘訣は、、
良き栄養でだんだん少食になりがちですが、腹八分目でなくたくさん食べましょうとおっしゃっていました。
もう一つは、3きょう
きょういく(きょう、行くところがある)
きょうよう(きょう、用事がある)
きょううん(きょう、運動する)
よく食べて、よく話し、趣味を持ち、外に出る。
おしゃべり最高、おせっかいもどんどんしましょう。
最後に笑顔と睡眠だそうです。
ストレスを溜めずに高田純次思考で!
元気に過ごしていこう!とパワーをもらえる講座は、多くの人が参加されて過去最多でした。
続きが聞きたい、また開催して欲しいとの声も上がる大盛況の講座になりました!
〜守谷市でのシニアの活躍の場を探る①〜
今回は市役所の市民協働推進課、企画課、健幸長寿課の方々にお話を伺いました。
まず、市の重点施策である「もりやビジョン」のうちの地域主導・住民主導のまちづくりについて紹介
市内の各地区の人口規模・年齢構成・歩んできた歴史が異なり、地区における課題も様々なので、求められる行政サービスも違うため、その地域に沿った行政運営が必要です。
例えば、みずき野地区の65歳以上の人口は52.6%を占めますが、松並青葉地区は4.5%なので、おのずと求められる行政サービスは異なりますね。
今後の「まちづくり協議会」の展望としては
①支え合い・助け合い活動
②多世代交流活動
③学校と連携した活動
④防災に関する活動
が大切です。
続いて企画課から、統計調査員について紹介
今年は、統計調査のなかで最も規模が大きい「国勢調査」が実施されます(5年ごとに実施)
守谷市は人口増加が続いているため、300名以上の調査員が必要とのこと。
関心がある方は是非、守谷市のホームページを検索してみて下さい。
続いて健幸長寿課から「シニアボランティア制度」について紹介
シニアボランティア制度は...
2025年最初の「いきいきシニアコース」は、
社会参加でいきいきシニア
〜"つながり"づくりで健康長寿〜
と題し、筑波大学の辻 大士先生から話を伺いました。
「介護予防教室」は来てほしい高齢者がなかなか来てくれないのが現状のようです。
65歳以上の高齢者で検診を受けていない人の割合は、男女ともに教育年数の短い人が多く、長く教育を受けている人の方が受診率は高くなっています。
さて、ここで問題です。
私たちの寿命は何で決まっていると思いますか?
寿命に与える影響の強さの順番としては……
(タバコやお酒ではなく)人とのつながりが最も寿命に影響を与えているようです。
調査によると、「スポーツグループへの参加割合が高い町は転倒者が少なく」
また「運動は一人ではなく、グループに参加して行った方が要介護状態になりにくい」そうです。
地域の集まりにただ参加するよりも「役割を持つ」ことで認知症リスクが低くなるとのこと。
高齢者の認知症リスクは、
自分が運動をしなくても「運動が盛んな地域に暮らすだけで低下」するという驚くべき結果が出ています。
社会参加が豊かな地域は人々のつながりが多く、助け合いや協...
守谷を知るコースの15回目は、
守谷市シルバーリハビリ体操指導士会の役割と活動紹介
まずは、「いきいきヘルス体操」について聞かせていただきました。
茨城県立医療大学附属病院名誉院長でもある大田仁史名誉院長が考案した体操であり、関節の運動範囲を維持、拡大し、筋肉を伸ばすことを目的としています。
座っても寝ていてもできる体操で、どこでも1人でも気軽にできます。
誰にでもできる体操とは素晴らしいです。
2004年から現在まで指導士の数は増え続け、令和6年度には10452人。
1級から3級までの資格があり、守谷市にも113人ほどの指導士の中に1級指導士が4名いるそうです。
出前サロンや体操教室など63箇所でシルバーリハビリ体操を指導して、2023年度の参加者は14467名とどんどん広がっています。
※発声練習の一覧表
講座のあとは、実際にみんなでシルバーリハビリ体操を体験しました。
1級指導士の方が教えてくれます。
92個の体操があるそうで、その中で座ってやる体操や立ってやる体操を体験。
座っていても、しっかりと体が伸びて体がやわらぎリラックスすることができました。
7人の指導士の方が来てくださり、体験中も指導していただき...
明けましておめでとうございます。昨年のお正月は能登半島地震で大揺れでした。能登では9月にも豪雨と洪水にも襲われ、甚大な被害に会いました。今年の正月は火事のニュースが多いです。戸締りと火の用心、お互い気をつけたいものです。インフルエンザの流行も気になります。手洗いうがいを徹底しましょう。
そんな中で、今年何となく気になっているのが「社会の変化についていけるか?」という漠然とした不安です。この問いかけには2つの意味が含まれていると思います。1つは同世代の人々の行動や考え方に自分はついていけているかどうか、です。頑張っている同世代には大いに勇気づけられます。もう1つの意味は、日本社会全体の変化に対応して自分の居場所を作っているかどうか、です。社会の原動力は30代~50代の働き盛りにありますから、この世代が牽引している社会を理解し、自分も役割をもって貢献しているかどうかです。特に高齢者にはこの問いが気になります。
残念ながら、一般的には高齢者や後期高齢者に上記第2の役割を期待するのは無理のようです(例外はあります)。最近、友人に勧められて「イノベーションの科学」(中公新書)という本を手にし...
情報配信をご無沙汰しております。。。
今年初めのゼミで、伊藤先生とは対面での開催でした。
3月8日(土)の最終発表会まで今日を入れて残り4回となりました。
参加者12名のテーマは下記の通りです。
残りのゼミでどうしていくか?
どこに着地するか?
次年度も継続するか?
などに関して、お一人ずつご意見をお聞きしました。
みなさん、今後やりたいこと、目指していることなど目的がはっきりしており、次年度継続する方もいるようです。
実際に、講座を開催している方や調査をしている方もいるようです。
ゼミの仲間からのご意見やアドバイスも熱心に耳を傾けていました。
伊藤先生からは、論文の書き方の講義がありました。
以下の流れで作成します。
テーマ(タイトル)
問題(目的、先行研究)
方法
結果
考察
引用文献
残りの期間で活動をまとめることになります。
学生さんファイト!!!
穏やかな散歩日和になった1月5日、葛飾柴又の七福神巡りに行ってきました。
TX 守谷駅に集合し、南流山駅から武蔵野線に乗り換えて東松戸駅へ。
そして北総線で京成高砂駅で降車。
男性8名、女性16名の計24名の参加でしたが、京成高砂駅には同じようなグループがたくさんいました。
まず、
①観蔵寺(寿老人)
②医王寺(恵比寿天)
③宝生院(大黒天)で記念撮影
④万福寺(福禄寿)
⑤題経寺(毘沙門天)こちらが有名な柴又帝釈天。さすがに混んでいました。
おみくじ販売も省力化?
帝釈天参道を通って
⑥真勝院真光寺(弁財天)へ。
最後は線路を渡って
⑦良観寺(布袋尊)へ。
あら?
布袋さんの御親戚が…笑
柴又駅まで戻って
寅さん像と、見送るさくら像にご挨拶
そのあと柴又駅で解散して、各自名物の草団子などを買って帰途に。
天候に恵まれて楽しい年初のイベントになりました!
守谷を知るコースの13回目は、クリスマス間近のスペシャルな講座。守谷市内で結成されている「ウィンドアンサンブル守谷」の講座がもりりん中央にて開催されました。
今年で結成26年むかえた吹奏楽団であるウィンドアンサンブル守谷は、35年ほど前の町主催の児童向け講座であった童謡教室が始まり。
音楽好きが集まっていて、そこから誰もが入団できて楽しめる楽団が結成されていったそうです。
1998年当時は15人だった団員は今では50人!定期演奏会は大人気で、もりりん中央では席が足りず、取手の会館で開催されています。定期演奏会の他にも冬の音楽会やクリスマスファミリーコンサート、市内のイベントに参加。演奏依頼も多く、地域の敬老会から子供が集うイベントまで引っぱりだこです。
講座の後半はたっぷり演奏を聴かせていただきました!
最初は元気いっぱい、思わず走り出したくなる「ウィリアムテル序曲」
しっとりムーンリバー、ディズニーの曲もあれば、みんな懐かしい昭和歌謡曲メドレー!
最後はジングルベルとあわてんぼうのサンタクロースでクリスマスムードばっちりで一足先にクリスマスプレゼントをもらいました。
そしてアンコールをお願...
守谷を知るコースの12回目は、毎年人気の講座。
「国際政治経済講座」
講師は常陽産業研究所チーフエコノミストの尾家さんでした。
「トランプ2.0の下での米国、石破政権の下での日本」
まずは、アメリカ大統領選の結果についてのお話でした。
トランプ氏返り咲きをどのように捉えるべきか。次期大統領候補と言われる、J.D.バンス次期副大統領や共和党上院院内総務ジョン・スーン氏の話やトランプ氏の政策などの話を聞かせてくれました。
また注目される人事や今後の世界についてなども、みなさん興味深く耳を傾けています。
そして、日本の選挙の話も。
自公過半数割れと国民民主党についてや、どのような政策が進むかなど日本経済についても話していただきました。
いま、みなさんが注目する話題が盛りだくさんで有意義な講座になりました。
人口減少時代のまちづくり
〈1コマ目〉
〇人口減少してもみんなが幸せになる、持続可能な社会の仕組みをつくることが大切
〇人口減が問題ではなく、人口減に対応する社会づくりができてないのが問題
(例えば、仕事が無いから若者が出ていくではなく、魅力がないから出ていくのである)
〇人口減を活かして、隣接する市と公共施設、医療の共有などうまく小さくして質を高める
これからは「AもBも」から「AかBか」へ
〈2コマ目〉
〇無作為抽出による自分ごと化会議
〇地域の中で特別に活動をしたり、積極的に発言したりしていない「普通の人」が集まる
そして自由に、思っていることを安心して話せる場
無作為抽出の市民で議論、条例も作る
「自分ごと化会議」は全国80自治体で180回実施された
無作為に選ばれた市民が判定人を務める行政事業レビュータイプと、
無作為に選ばれた市民が地域のテーマについて話し合う住民協議会タイプの二つがある
〇信頼関係にもとづく対話で、修正可能な柔らかい社会決定をめざす
講義最後30分は短い時間ですが、学生による質問及びデスカッションが行われました。
ノーベル平和賞を受賞した被団協の田中熙巳(てるみ)さん(92才)の受賞講演最後の言葉に注目しました。「人類が核兵器で自滅する事のないよう、そして核兵器も戦争もない世界の人間社会を求めて共に頑張りましょう。」というメッセージです。一瞬、スピーチの最後を飾る軽い挨拶のようにも聞こえましたが、反芻してみるとかなり重い言葉が発せられたと思いました。そこで、「人類が核兵器で自滅する」という想定を数字で捉えてみることにしました。
現代の核兵器は広島型の1000倍や1500倍もの威力を発揮するものもあるようですが、米国が現在開発している新型爆弾は24倍だそうです。広島では昭和20年8月6日に原爆が投下され、その年の12月末までに14万人の死者が出たと記されていますから、仮にその24倍の威力を持つ新型爆弾が投下されたら14万人×24=336万人の死者が出ると推定されます。そして世界の核兵器数はおよそ12700位あるそうですから、336万人×12700≒426億人になります。地球人口は多く予想しても100億人止まりですから、地球人口の4倍を殺傷することができる、ということになりましょうか?
田中さんがおっしゃった「人類が核兵器で自滅する」という...
防災ファシリテーター養成講座
国立研究開発法人防災科学技術研究所 李泰榮(いてよん)講師
〈1コマ目〉
地域防災における「自助」「共助」「公助」
災害時の「公助」の公的支援は、「すぐに」「すべての地域ヘ」は届かない。
自主防災組織制度の創設
地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」
〈2コマ目〉
地域の災害危険性を調べる
守谷市のハザードマップなどを学生それぞれPCで検索実習
〈3コマ目〉
地域防災の取組支援に必要なこと
【事例】被災経験を活かした防災対策の検討支援
【演習】学生ひとりひとりワークシートの作成
3コマの講座では、学生の主体性を重視した、ファシリテーター養成講座となりました。
秋晴れの11月22日(いい夫婦の日)に夫婦じゃない人13名が歩いてきました
9:05 守谷駅始発のTXで南流山まで行き→武蔵野線に乗り換えて新松戸へ→常磐線各駅停車で北小金で下車。
マツモトキヨシさん発祥の小金宿から東漸寺へ。
なかなか趣のあるお寺です。
まずは参加者全員で記念撮影
樹齢340年の桜の木が枯れてしまったので、10/1 に新しい樹齢50年の「センダイシダレ」を植えたそうです。
ひと通り散策後、北小金駅の反対側の本土寺へ。
紫陽花寺として有名な本土寺ですが、紅葉の時節もキレイだということで訪れたのです。
が、、、
暖かい日が続いたせいか紅葉は今ひとつという感じだったから?
本来500円の参拝料が今日は無料開放でした(^^)
それでもあちこち少しずつ紅葉が始まっていました
本土寺参拝後は現地解散とし、それぞれが参道沿いのお店で買い物をしたり、草団子を食べたりして帰途につきました。
晴れてよかった‼️
今回の公開講座は、アーカスプロジェクトのオープンスタジオツアーに参加しました。
アーカスプロジェクトは30周年、毎年国内外から3組のアーティストが守谷市に3か月滞在をして作品を作り上げていきます。
今年は世界から534件の応募があったそうです。その中から選ばれたアーティストの作品を見るだけでなく、本人に会えて、タイミングが合えば話を聞くことができます。
スタジオ1は、インドネシアから来ている「ハイフン」7人組のリサーチグループ。
文筆家で劇作家のダナルトのアーカイブ制作です。
ダナルトの足跡を追い、黒板には年表とその時々の出来事が記されていました。
書籍やイメージされたものなどの図書館です。
スタジオ2は、丹治りえさん
現在のひたち海浜公園は、1973年まで水戸射爆撃場として米軍の軍事演習に使われていたそうです。
その時代の子供達の作文展示や沖縄の米軍基地を臨む部屋を再現したパネルがありました。
スタジオ3は、エヴァ・ザイラーさん
日本は人間と昆虫の関係が近い文化だと思い、蚕に着目したそう。天井からは蚕の糸がいくつも下がっていて不思議な空間を作り出していました。
機織り機のようなものにも...
もりや市民大学では学園ニュースを発信しているのでご存じの方が多いと思いますが、今回は「守谷を知るコース」第14回目にて茨城県自然博物館訪問の校外授業のニュースでした。私もこの校外授業に参加しました。340円の入場チケットを手に入館すると、直ちに研修室へ入室、そこで、守谷の昆虫の話と守谷の植物の話を聞きました。もとは守谷市と周辺市内の小学校教員だった石塚先生による昆虫のお話と学芸補助員の飯田先生による植物のお話、詳しくは学園ニュースをご覧ください。両先生は「守谷野鳥のみち」のガイドも引き受けて下さっているそうです。
オサムシの話には驚きました。マンガの巨匠、手塚治虫がオサムシの大ファンであり自分のペンネームを手塚オサムシにしたがった、という話です。オサムシに引っ掛けて治虫という名前にしたそうです。初耳でした。でも、それよりもっと私が注目したのは、石塚先生が何気なくおっしゃった「世代交代が早い昆虫は発展するのですよ」という一言でした。昆虫の多くは一年に一度の世代交代ですが、種類によっては一年に複数回世代交代できる昆虫もいるそうです。そして、そのような昆虫はより大きく繁栄するというのです...
今回は「守谷における動植物」と題し、茨城県自然博物館での校外学習でした。
毎週土曜日は小中高生は無料で入館できるということで、県外からのお客さまもたくさん訪れていました。
20名以上の団体で70歳以上だと340円で入れますので、市民大学の学生さんは多くの人が恩恵を受けられます(^^)
講義は「スタディルーム」で受講
まず、かつて守谷市内の小学校で教鞭をとられていたという石塚さんから、守谷市での昆虫の調査についてお話を伺いました。
平成5年から11年の調査では、なんと守谷市内に705種類の昆虫がいたそうです。
しかしながら、ハルゼミやイトトンボの仲間、オサムシの仲間は激減し、新しく南方系の昆虫(ツマグロヒョウモンなど)や外来昆虫が新しく定着しているそうです。
「あれ、マツムシが鳴いている〜♫」という歌がありますが、このマツムシも準絶滅危惧種です。
続いて「守谷の植物」について学芸補助員の飯田さんからお話を伺いました。
守谷での消えゆく植物には、薬草であるセンブリ(胃薬)、ウツボグサ(腎臓の薬)、ゲンノショウコ(胃腸薬)などがあり、
茨城県最後のオキナグサは、かつてのクレノートン跡地...
今回の講座は、「ものづくりで認知力アップ」ということで、筑波大学附属病院の認知力アップデイケアに勤務されている、作業療法士の羽田舞子先生にミニ体験型講義をご担当いただきました。
考えながら、手先を使って何かを作り出すことは、脳にとって良い刺激だそうです。
ものづくり?ということは、何か作るのですね!!!
さて、何を作るのでしょうか?
今回は、2つの作品を作りました。
まず一つ目。
美味しそうな黒豆大福
と思いきや、カードフォルダーです。
大福の部分は粘土を使って作成します。
黒豆は、黒の粘土を練り込みます。
思わず、食べたくなっちゃう!おいしそうな黒豆大福ができました。
続いての作品は、これです。
まずは粘土をこねます。
次に色を付けます。
さらにこねます。
そしてできたのは、、、
個性豊かな、かわいらしい“ウサギさーん”
先生の見本を見ると、簡単にできそうな気がしていましたが、実際にやってみると、形を作るところや尻尾をつなげるところなど意外と難しかったようです。
粘土が固まってしまうので、時間との勝負でしたね!
次の兎年には飾りましょう♪
育休パパ・ママの職場復帰セミナー
職場での仕事やコミュニケーションの方法、パートナーとの役割分担、さまざまなサービス利用など、育児と仕事の両立のためのポイントを解説します。経験者の体験談や参加者同士の交流会もあります。パートナーとの参加も歓迎です。▶日時・場所 ①12月18日(水)10:30~12:00 市民活動支援センター 会議室(ZOOMでの参加可能です) ②12月21日(土)10:30~12:00 北守谷児童センター 視聴覚ルーム ※講義内容は両日とも同じです。都合のよい日時を選んでお申込みください。▶講師 宮下嘉代子(市民科学ゼミ生、キャリアコンサルタント)▶対象 育休中の方、復職を検討されている方▶定員 各先着20組(親子で参加可)▶参加費 無料▶申し込み方法 11月18日(月)~12月4日(水)までに「参加申し込み⇒クリック」から申し込む▶問い合わせ先 市民大学ホームページのお問合せフォームからお願いします。 参加申し込み⇒クリック
守谷を知るコースの10回目は、アート/守谷の遊び方。
市内在住の植物画家である本田尚子先生の講座でした。
本田先生は子供の頃から虫好きで「虫めずる姫」と呼ばれていたそうです。
守谷の里山の虫たちの四季
季節ごとに咲く花々と共に虫たちを紹介してくれました。とても繊細で美しい絵にうっとりしながら、季節によっていろいろな虫が住んでいること学びます。
生きている虫しか描かないという先生は、カメラを持って市内を散策。
小さな虫を撮るのは困難な気がしますが、花の蜜を吸ってる時や交尾している時は集中していて、ひなたぼっこしているとリラックスしていて、その時が狙い目だそう。気配を消して、捕まえないわよ〜という気持ちで撮ってるそうです。
虫の種類や生態などにも詳しく、虫のたくましさや多様な特性についても教えてくれました。
自分を守るために木や葉っぱと一体化している虫や蜂に体を似せている虫など、なるほどです!
守谷にこんなにも多くの種類の虫たちが住んでいるとはビックリ。
家の庭や畑、森林公園や鳥のみち、利根川河川敷など身近にいるのですね。
今回の講座にあわせて、教室である支援センターで本田先生の原...
守谷を知るコースの9回目は、「人はアルカリ性体質の動物」
食による健康推進研究所の長谷山先生の講座でした。
人の体質は人間が誕生したころと変わっておらず、アルカリ性の動物で体を食でアルカリ性にしておくと病気をうまず、健康でいられるそうです。古代の食は果実中心の生の植物食だったのでアルカリ性の体であり、そこは今でも変わらないのでアルカリ性の体にしておくと健康に。
植物性食品とは、生野菜や果物、海藻類、大豆、きのこ類、発酵食品など。小麦は植物ですがダメだそう。動物性食品は、肉や卵、魚、砂糖、加工食品、食品添加物など。
動物性を多く摂取すると酸性度が高まり不健康や病気を促すのだとか。
毎日、生野菜(サラダ)を食べると良いそうです。火を通すとアルカリ性が減ってしまうので。
アルカリ性と酸性の食品一覧。
赤ワインや焼酎は良いのですね!
「植物を丸ごと食べる」と老化をくい止め、「若返りもする」
植物丸ごと食は健康寿命の本命だとおっしゃっていました。
健康になるだけでなく、若返る⁈もっとサラダを食べようと思いました!
今回は、「自治会・町内会」について、
「まちづくり協議会」とよく似た団体、その違いと役割
「自治会・町内会」の紆余曲折
全戸加入原則と公的な役割を自ら引き受ける民間団体
行政に協力しても特別扱いされない任意団体
「自治会・町内会」の功績
積極的に行政に協力することで、むげにはできない存在に
改めて「まちづくり協議会」の本当の意味での役割は何だったか
「自治会・町内会」から継承すべき側面、「まちづくり協議会」が克服しなければならないこととは何か
2回にわたり、実践的というよりも、原理的なお話しの講義でした。
2015年9月の国連総会で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)は、地球の問題や課題を地球に住むすべての人たちで解決する社会づくりをめざし、2030年までに達成すべき目標を17件掲げました。さあ、「17件を全て言ってください」と言われて正しく答えられる人、いますか?1番目は「貧困をなくそう」です。6番目には「安全な水とトイレを世界中に」というのもありました。16番目は「平和と公正をすべての人に」もありました。こんな調子で、言われてみれば成程、といった目標が17件に纏められています。
その2030年まであと6年です。改めてSDGs17目標を眺めてみると、あと6年で実現できるような気がしません。逆に、目標から遠ざかっているような現実があるように思います。たとえば、先ほどの16番目の目標について言えば、世界は平和より戦争に向かってずるずると引き込まれているようです。あと6年で全ての人に平和と公正がもたらされるとは、残念ながら期待できません。そんなSDGsですが、11番目の「住み続けられるまちづくりを」という目標については、守谷市でも考えることができます。
SDGs11番目の目標「住み続けられるまちづくりを」では個人の意識、個人...
あたまが喜ぶ体験として、今回は「パーソナルカラーを知っておしゃれを楽しみましょう♪」というテーマで、ケアービューティストの尾形直美さんにご講義いただきました。
ケアビューティストとは、高齢者や介護が必要な方に向けて、美容の技術(ネイル・メイク・エステなど)を通して自分らしく前向きな気持ちになれるようお手伝いする、「介護美容のスペシャリスト」だそうです。
「服装や流行への関心が高いシニアは、町内活動やボランティア活動に積極的に参加しており、活動能力や生きがい感も高く、メンタルヘルスも良い」
という研究結果が出ているとのことなので、おしゃれをすることは、認知症予防にもつながりそうですね!!
そこで今回は、各自のパーソナルカラーを調べて、おしゃれに生かしましょう。
ということで、まずはパーソナルカラーって何?というところから教えていただきました。
続いて、簡易的なチェックをしました。
結果は、4つの季節のイメージカラーに分けられるそうです。
参加者からは、最近おしゃれしていないから、少し意識してみようかしら?というお声がありました
ぜひとも、各自がワクワク★ドキドキできるものを身...
「ようこそ守谷へ」の紹介
守谷市に転入した方が一日も早く地域に溶け込み、一人ひとりが守谷を第二の故郷と感じていただけるよう、市、市民活動団体等による情報発信と地域における仲間づくりの場の提供を目的として開催する歓迎イベントが「ようこそ守谷へ」です。
今回は守谷歴41年という実行委員長の実好敏正(さねよしとしまさ)さんにご紹介いただきました。
実好さんは周りの人から推薦されて委員長になったそうですが、「新しく守谷に転入した方は不安を抱えているので、人と友だちになる機会を作ってあげたい」と考えていたそうです。
転入された方に「なぜ守谷を選んだか?」を伺うと、
・自然がいっぱいで緑が多い
・コンパクトで便利な街
・道路が広くて運転しやすい
・イベントが多くて楽しい
・地盤が強い
などなど、いろんな答えが返って来るのが楽しくて、、、
中には「木造の綺麗な守谷小学校に子どもを通わせたいから」という答えもあったそうです。
ただ2020年のコロナ禍では一同に会することが難しくなり、YOUTUBEの生放送で実施。
今年は11月16日(土曜日)に開催予定!
コロナ禍以降は規模を縮小して、身の丈に合った規模感で実施...
子育て中のパパ・ママ向け講座
子育てに関する行政支援・行政サービスについて、コンパクトにまとめた講座です。赤ちゃんをだっこして一緒に受講できます。
▶日時 11月2日(土)、11月7日(木)10:30~12:00 講義内容は両日とも同じです。都合のよい日時を選んでお申込みください。▶場所 北守谷児童センター 視聴覚ルーム▶講師 のびのび子育て課 職員▶内容 ・妊娠から検診までの支援、サービス・申請 ・利用できるサービスや施設のご紹介 ・子育ての相談窓口 ・赤ちゃんマッサージやふれあい遊びを通じて大切にしていること(実践)▶対象 市内在住の妊娠中~生後半年までのお子さんがいる方▶定員 20組(親子で参加可)※超過の場合抽選▶参加費 無料▶申し込み方法 10月24日(木)までに「参加申し込み⇒クリック」から申し込む 受講の可否は10月25日(金)までにメールで通知します。▶問い合わせ先 市民大学ホームページのお問合せフォームからお願いします。
参加申し込み⇒クリック
地域自治としてのまちづくり協議会
放送大学教養学部教授 玉野和志氏により講義が行われました。
〈第一回目〉
学生による意見交換が行われました。
(4)守谷市の説明は,どうなっているか
• 設立後のイメージ
• 「まちづくり協議会」活動の流れの例
• 行政が解決,行政との協働により解決,各団体の連携・協力で解決
• 「地域自治組織」へ発展することを期待
• 行政のパートナー
(5)本当にそんなことができるのか
• 疑問を出し合おう
• 「地域自治組織」へ発展するとはどういうことか
• 行政の役割はどこにあるのか
行政との協働こそが問題ではないのか
(6)行政の思惑
• 行政ができることの限界
• 住民主導ではなく,住民による負担が必要な事情
• 他方で,行政以上に弱っている住民の担い手と活力
• 実現可能な道はどこにあるか
(7)本当の意味での「まちづくり協議会」の役割
• 具体的な活動ではないこと
• 住民にできることは少ない,各団体はすでにやっている
• 行政がやるべきことの要求
• それと引き換えにできることの負担
• 行政と市民の役割分担を交渉して決定すること
【何かひとつでも良いから実現すること】
zoomの生徒はチャットでの参加、...
守谷を知るコースの7回目は、「ふるさ都市もりや朝市」を企画・運営している、末留さんと横山さんの講座でした。
毎月、守谷駅西口駅前広場で開催されている「ふるさ都市もりや朝市」は、飲食やハンドメイド、ワークショップ、体験などで盛り上がっている朝市です。
末留さんと横山さんが中心となっている、イベントプロジェクトチーム「Hello every one!」は2024年1月に設立して、守谷駅前だけではなく常総運動公園やジョイフル本田守谷店などでも開催し、幅広く活躍されています。
参加店舗は季節や天候によって20〜80店舗、経済効果は1回で40〜290万円で2023年度は15回開催して約3000万円!すごいです!
ただ毎月開催するだけでなく、月毎にテーマがあって目玉イベントがあるのが飽きさせないコツなのでしょうか。
駅前広場で開催することにより、地域住民の交流の場となり、作り手と買い手のコミニュケーションの場となり、駅前活性化につながっているのですね。
市内の飲食店が多く出店されているので、朝市で食べて知って、店舗に食べに行く方も多いそうです。
市内の飲食店の味を知るきっかけにもなっています。
元気いっぱいな横山さんは末留さ...
「心と頭に響く音楽体験」
今回は昨年に引き続き、音楽療法士の佐々木宏子さんにお話を伺いました。
先ずは前回の復習として
・音楽療法とは
・音楽の効果
・音楽療法の対象者
・認知症予防
・音楽療法士とは
について触れ、受講者に「普段から歌を歌いますか?」と問いかけたところ、「歌は聴くけど、歌うことはほとんどない」という方が多かったようです。
今回もいろんな楽器を準備して下さいました。
最初は発声練習からスタート!
ア・イ・ウ・エ・オ〜
会場の市民ギャラリーに受講者の声が響き渡ります♪
皆さんよくご存知の「炭坑節」の曲で「赤とんぼ」の歌詞を歌って、次に「赤とんぼ」の曲で「炭坑節」を歌いました。
これはトーンチャイムという楽器です。
「私はどの音程のチャイムを使ってみようかしら?」
皆さん一生懸命ホワイトボードを見ながら音を出していました。
一緒に歌ったり演奏することで、コミュニケーション、協力、社会的認知、結束などの「社会的機能の実践」に参加することができ、思い出のメロディが無意識に自伝的記憶を喚起できるそうです。
男性は中学〜高校の時に、女性は小学校高学年の時に、音楽が一番影響を与えると...
守谷を知るコース6回目は、校外授業でした。
守谷高等学校に伺って、剣道部総監督である塚本浩一先生の講義です。
土浦出身の塚本先生は、昭和63年に守谷高校へ赴任されて、一度は他校に移動されましたが、平成19年に守谷高校に戻り36年に渡り剣道部の指導されております。
守谷高校に赴任当初は県大会ベスト8が最高でしたが、剣道部就任2年目で県大会ベスト4、関東大会で初出場で初優勝の大快挙!
関東大会優勝が先で県大会は5年かかったそう。
初の全国大会は予選敗退、そこから17年をかけて優勝に導き、12回の優勝、13回の準優勝という素晴らしい成績です。
武道は九州が盛んで、もちろん強い。
その中で勝ち続ける守谷高校剣道部は、全国でも有名ということが納得です。
今年も九州・福岡で開催された由緒ある大会である「王龍旗高校剣道大会」で準優勝。
トロフィーも見せていただきました!
年月を重ねるごとに強くなっていった守谷高校剣道部。
県内だけでは強くなれないと、大きな大会に参加させて度胸をつけて、プレッシャーに負けないように遠征をしていたそうです。
県立ですので、私立のような援助がない中、塚本先生の自腹を切ることもしばし...
地域課題の発見と対応推進方法の講義最終回
「力を引き出す」ための考え方と技術
ダメ会議の経験談を学生同士で1分間話し合う。どんな意見が出たのでしょうか。
学ぶ事は
会して⇒議して⇒決して⇒動く
【仲間とともに事業をすすめる際に必要となる「対話力」「会議力」を学ぶ】
講義の最終回、いままで学んだ事を学生同士で15分間話しあいが行われます。
早速、議する:空間のデザイン⇒席の配置
決する:可視化⇒A3の紙に太いマーカーで書きながら話し合うことで「見える化」を学ぶ
4回の講義で学んだことで実際に〈対話〉が出来ましたか。
zoomの生徒同士ではブレイクアウトルームで〈対話〉してもらいました。
講義で学んだ考え方と技術、今後の活動に活かせる事と思います。
2ヶ月にわたり、徳田先生ありがとうございました。
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.RoomsLanguage.display_name}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}
{{item.Topic.display_summary}}