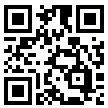もりやいきいきコースの第7回目は、「新年準備と里山の正月飾りワークショップ」
講師は守谷里山ネットワーク代表の清野さん。
始めに日本のお正月についてのお話がありました。お年玉は昔は、年神様にもらうお年(歳)玉。一年が始まり歳をもらい、みんなと一緒に歳をとるという意味だったそう。そして門松やしめ飾り、鏡餅の風習のお話など、これから年末年始に向けての心構えができます。
その他に清野さんの活動として里山活動や以前の市民大学での講師時の話、現在はもりや市民大学の科学ゼミで利根川グリーンインフラの研究講座も勢力的に動いているそうです。
後半はミニしめ縄つくりのワークショップ。立沢里山の蘖(ヒコバエ)をたくさん用意してくださいました。
受講生のみなさんは悪戦苦闘しながらも、しめ縄つくりに挑戦。
材料は同じなのに、出来上がりがみんな違ってたった一つのしめ縄飾りができました。
これで正月準備はバッチリですね!
2040年 日本はどういう社会を迎えるか
地域包括ケアシステム
「ふだんの暮らし」とは?
暮らしの一部
⇒専門職は、「イベント」「制度」「サービス」 「仕組み」に乗ってきた人しか支援できない
重要なのは、「非日常」(イベント)だけではなく、
「日常(生活)」(イベントに参加していない)を育むこと
「日常」に寄り添えるのは、同じ地域に暮らす住民
人口減少や繋がりの希薄化が進む中で
支え合いの地域づくり、住民主体の地域づくいをどう進めるか
できれば高齢化を話題にしたくないと思っています。クラス会や同窓会の集まりに参加したとき、高齢化やそれに伴う病気、怪我の話が始まるともう止まりません。治療の経過などを詳細かつ具体的に語るご仁もおられ、途中でそのお話の腰を折る訳にもいかずじっと拝聴するばかりです。そうなることを見越して、場合によっては「今日は健康と病気の話は無しにしよう」と前置きをしたこともありました。
では、どんな会話が楽しいでしょうか?一番良いのはすぐ先に予定している行動の相談です。前向きというより、それなしには先へ進めない切羽詰まった話し合いにもなりますが、とても具体的です。時間や場所、準備手順などを会話します。こういう時、参加者は年齢や病気の関心事から離れ、目の前の現実に集中しますから、思い出話に花を咲かせるわけにはいきません。こういう場面を持つことは、高齢者にとっても良いことかと思います。
ボランティアの打ち合わせ会議、趣味グループのイベント相談会議、スポーツチームの次回試合への打ち合わせ、などなど、楽しい会話場面を沢山作り出すことは、街の活性化に繋がります。守谷市民活動支援センターはまさにこう言った...
子ども食堂のつくりかた
・子ども食堂を知るための研修
⇒どのようなかたちを作りたいのか
・場所の確保
・食品衛生責任者
・保健所への相談、手続き
・検便の実施
・衛生研修等研修への参加
【食を通じたさまざまかたち】
・テイクアウト
・デリバリー
・フードバンク
・フードドライブ
手作り折り紙のプレゼント
防災食(ビニール袋で調理)
寄付していただいた食材で調理
ビデオ視聴で発足当初からの活動紹介も、様々な活動のお話しは大変興味あるものでした。
もりんくるのねがい
・子ども食堂の必要性
「こういう地域であってほしい」で子ども食堂のかたちは多様
一人では大変でも誰かとなら作れる同じ思いの人はきっといる
・子ども食堂啓発活動
興味を持ってもらうこと、やってみたいと思う人を応援
・小学校区域に1つ以上の「子ども食堂」 「地域食堂」
公開講座・第4回目
守谷の「新しい幸せスタイル」を考える。
茨城県生涯学習・社会教育研究会会長である長谷川幸介先生の講座でした。
町と村が合併し、守谷町になり、守谷市になり、どんどん発展してきた守谷市。
日本で核家族ができた過程はNY万博の時に考え方が出された郊外型住宅団地だそうです。
郊外型住宅団地の形成と守谷市政の「幸せのカタチ」
郊外型団地の特性と反乱
「郊外」を超えた「幸せのカタチ」
守谷のいままでと市民協働の歩みなど聞かせていただきました。
どうやって幸せのカタチを変えていくのか、、、
最後に
「生き残ったのは、頭がいいのではなく、力が強いのでもない、変われた者だけが生き残ったのである」(C・ダーウィン)の言葉をおっしゃっていました。
変わるのは簡単そうで難しいですが、心に留めておきたいと思いました。
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.RoomsLanguage.display_name}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}
{{item.Topic.display_summary}}