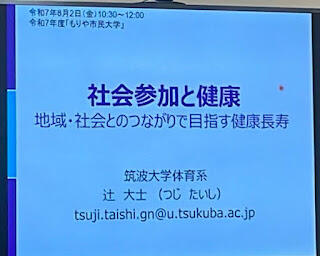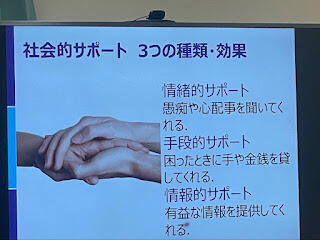みんなのまちづくり入門コース(3回目)
社会参加と健康
地域・社会とのつながりで目指す健康長寿
筑波大学体育系 助教 辻 大士(つじたいし) 氏
予防医学健康増進科学の専門家であり、地域環境や社会の仕組みが健康に与える影響を研究なさっている経験から、今回は『市民側の視点』に焦点を当てて講義をして頂きました。
≪「介護予防教室」は有効か?!≫
〇 ハイリスク者を特定して運動教室や栄養改善教室に参加させる戦略
〇 期待された参加率5%に対し、実際は0.2%程度と効果が限定的
⇒ リスクの高い人々を適切に把握できない
⇒ 対象者が「まだ大丈夫」と参加を拒否する傾向
≪予防医学の新しい流れ≫
〇 環境やまちづくりへの着目
〇 社会参加が健康に良いという観点の重視
〇 2つの柱
①「個人」の行動と健康状態の改善(規則正しい生活習慣の確立)
②「社会」環境の質の向上
⇒ 社会との繋がりと心の健康の維持・向上
⇒ 誰もがアクセスできる健康増進基盤の整備
≪健康なまちづくりの進め方≫
〇 社会的サポートのメカニズム
⇒ 情緒的サポート : 心の支え、悩みを聞いてもらえる関係
⇒ 手段的サポート : 実質的な助け合い(金銭的支援など)
⇒ 情報的サポート : 日常生活や地域に関する有益な情報共有
〇 地域活動参加の健康効果
⇒ 地域の活動(スポーツ、趣味、町内会など)に参加している人は、参加していない人に比べて要介護状態になるリスクが75%低い
⇒ 役割を持つことの重要性
〇 地域全体への波及効果(地域活動の社会的影響と波及効果のメカニズム)
⇒ 健康に良い行動が「伝染」しやすくなる
⇒ 健康に良い雰囲気が「醸成」される
⇒ 健康に良い環境が「整備」される(施設やシステムの改善)
〇 通いの場の効果
⇒ 一つの活動参加がきっかけとなり、他の活動にも参加するようになる連鎖効果
※講義の最後には、具体的にどんな「行動」を実践すればよいか、例示してくださったので、質疑応答も皆さんが「自分事」として語らえる濃い時間となりました。